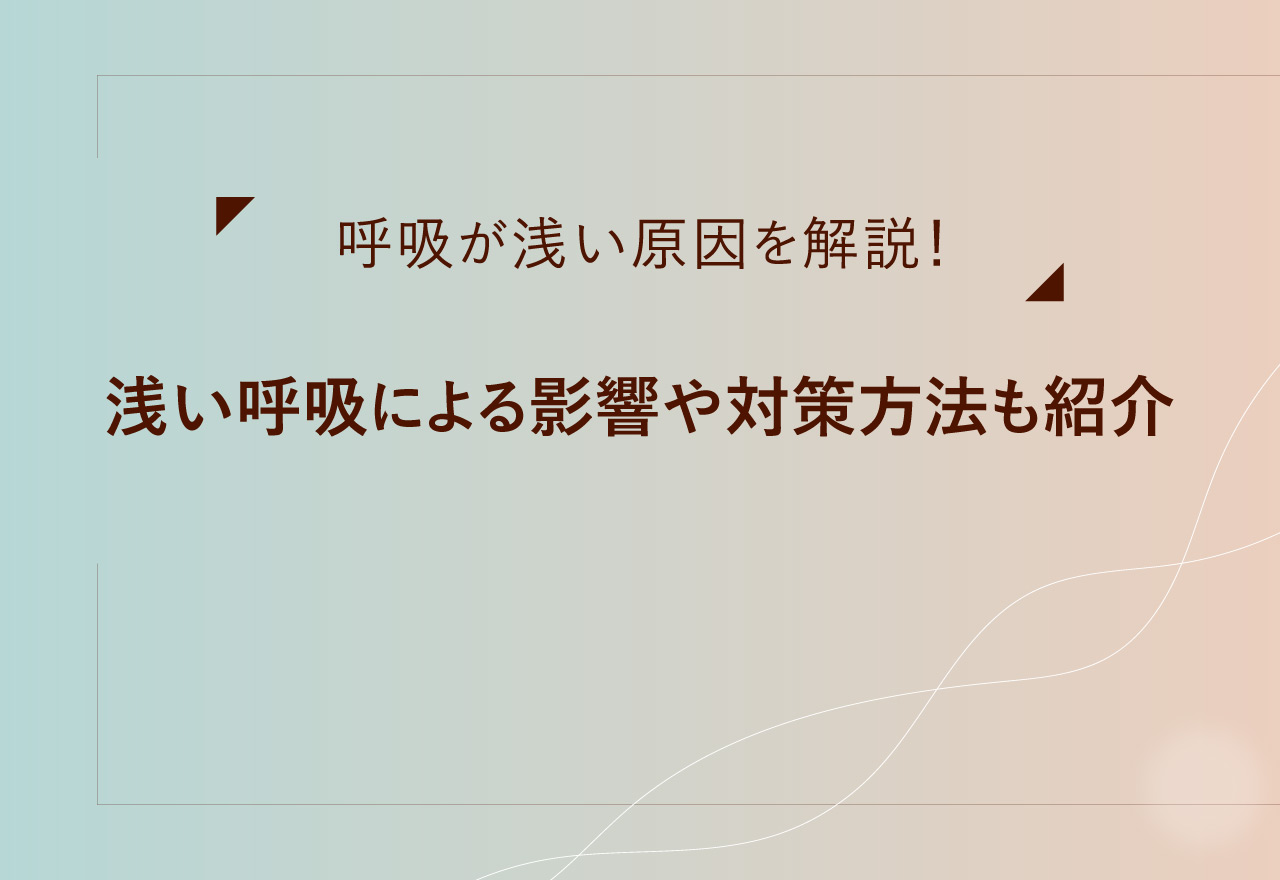目次
呼吸が浅い原因
呼吸が浅い原因として、以下が挙げられます。
- 過度なストレス
- 悪い姿勢
- 運動不足
- 病気
過度なストレス
呼吸が浅い原因の1つとして、過度なストレスが挙げられます。
ストレスが多い現代の社会生活では、不安やプレッシャーを感じやすいと言えます。その場合、交感神経が優位になるシチュエーションが増えるため、浅い呼吸になる可能性が高いです。
例えば、ストレスを感じると、意識とは関係なく、浅く速い呼吸になることがあります。これは、脳内で呼吸と感情をコントロールする器官が同じであるため、感情に合わせて呼吸も影響を受ける仕組みによるためです。
このような現象は「情動呼吸」と言われています。「情動呼吸」は、ストレスの悪循環を引き起こしてしまうことがあるため、注意が必要です。
さらに、不安やプレッシャーを感じて、呼吸に携わる筋肉が硬くなると、浅い呼吸を誘発しやすくなります。そうすると、浅い呼吸が不安やプレッシャーを引き起こすという悪循環が生まれてしまいやすくなるでしょう。
悪い姿勢
呼吸が浅い原因は、悪い姿勢とも言われています。
デスクワークやスマートフォン、パソコンの使用を長時間続けると、姿勢が悪くなりやすいです。このとき、胸郭の動きが制限されるため、腹式呼吸が難しくなり、結果的に浅い呼吸になる可能性が高いです。
具体的には、同じ姿勢が長時間続くと、いつの間にか猫背になってしまうことがあります。猫背は、呼吸にとって理想的な姿勢とは言い難いです。なぜなら、猫背では、肩甲骨が本来あるべき位置になく、胸郭が広がりにくいためになります。
そのため、深くゆっくりとした呼吸になるように、姿勢を改善すると良いでしょう。
運動不足
呼吸が浅い原因の一つに、運動不足が挙げられます。
運動不足になると、呼吸に関わる筋肉、いわゆる呼吸筋の働きが弱まり、呼吸が浅くなると言われています。また、運動不足の状態では呼吸筋のみでなく、心臓の動きも弱まる傾向にあり、呼吸が浅くなりやすいです。
自分に合った運動を少しずつ続けることで、筋肉や血流の改善が見込めます。具体的には、ウォーキングやランニング、水泳などの有酸素運動は肺活量を増やすため、呼吸筋が強化されると言えます。
運動不足が解消すると、浅い呼吸が徐々に減る可能性が高くなるでしょう。
病気
呼吸が浅い原因は病気を患っているケースがあります。
病気由来の浅い呼吸は「呼吸困難」と言われる症状を指しています。例えば「苦しい呼吸」「空気を吸い込みにくい」などの症状で、感覚や表現には個人差があります。病気による呼吸困難は「急性」や「慢性」、「安静時」や「運動時」といった発症時の状態を把握することが重要です。
呼吸器系疾患の多くが呼吸困難を引き起こします。体内の臓器の異常を知らせるように、呼吸にも異常が起こると言えます。 呼吸器系疾患の例と特徴は以下の通りです。
| 病名 | 特徴 |
| 気管支喘息 | 気管支の収縮により気道が狭くなる症状 |
| COPD(慢性閉塞性肺疾患) | 喫煙習慣が主な原因 |
| 市中肺炎 | 普段の生活の中で感染・発症した肺炎 |
| 肺線維症・間質性肺炎 | さまざまな病気を含み、難病の特発性肺線維症が多い< |
| 肺がん | 進行すると呼吸困難を発症 |
| 胸水貯留 | 肺を覆う胸膜に体液がたまりすぎている状態 |
一方で、呼吸器疾患以外の例と特徴は以下の通りです。
| 病名 | 特徴 |
| 心不全 | 心臓のポンプ機能が弱まり、全身に必要な血液を上手く送り出せなくなる状態 |
| 狭心症・冠動脈疾患 | 冠動脈の狭窄などが原因で虚血状態に陥る |
| 貧血・慢性出血 | 血中のヘモグロビンが減少し、酸素不足が起こる |
| 神経筋疾患 | 筋ジストロフィーなどの疾患により呼吸筋に影響が及ぶ |
| 過換気症候群 | 激しい運動や精神面での不安により必要以上に呼吸を行う |
上記に挙げたものの中には、処置に緊急性を要するものがあるため、発症したら速やかに受診すべきでしょう。
呼吸が浅いことによる心身への影響
呼吸が浅いことによる心身への影響として、以下が挙げられます。
- 自律神経のバランスが乱れる
- 病気にかかりやすくなる
- 精神が不安定になる
- 代謝が落ちて疲労を感じやすくなる
- 筋肉にダメージが生じる
- 体が冷える
- 集中力が落ちる
自律神経のバランスが乱れる
呼吸が浅いと、自律神経のバランスが乱れる傾向にあります。
自律神経は、体内の機能を無意識に制御する神経システムのことです。「交感神経」と「副交感神経」の2つに大きく分けられます。
呼吸が浅い状態では、交感神経が優位に働き、体に緊張をもたらすと考えられています。交感神経が優位に働きすぎると、副交感神経の働きが抑えられてしまい、自律神経のバランスが崩れた状態になってしまうことがあります。その場合、保っていた体内のバランスも崩れやすくなると言えます。
交感神経は「加速装置」、副交感神経は「減速装置」のような役割と考えられています。この2つの神経のバランスを保つことで、体内の器官が正常に働くと考えられています。
例えば、副交感神経の働きが抑えられると、胃腸の働きが弱まったり、睡眠に支障が出たりします。また、自律神経のバランスが乱れると、食欲不振や血流悪化、めまい、息切れ、動悸なども引き起こす場合もあります。
病気にかかりやすくなる
呼吸が浅いと、病気にかかりやすくなると言われています。
浅い呼吸による自律神経のバランスの乱れから、睡眠中も交感神経が優位な状態に陥りやすくなります。また、浅い呼吸のままでは、体をリラックスさせることができず、結果的に睡眠不足になることが多いです。
睡眠不足の状態では、弱った細胞や臓器の修復を司る、成長ホルモンが分泌されにくくなります。加えて、呼吸が浅いために血流が悪くなり、体内に血液や酸素を行きわたらせることが難しくなります。結果として、免疫力が低下し、病気にかかりやすくなると言えるでしょう。
そして、弱った細胞や臓器は細菌やウイルスに攻撃されやすいため、感染症や病気にかかる可能性が高いです。
成長ホルモンは日中はほとんど出ておらず、睡眠中に分泌されるため、睡眠時間の確保が健康につながると考えられています。
精神が不安定になる
呼吸が浅いと、精神が不安定になるケースがあります。
浅い呼吸により、交感神経が活性化されると、ストレスの原因となるホルモンと呼ばれるコルチゾールが増加すると言われています。また、浅い呼吸を原因とする睡眠不足によって、睡眠中の記憶整理が行われない状態になります。そうすると、ネガティブな感情が残り、不安やイライラを感じやすくなるでしょう。
人は睡眠中に不要な記憶を消去し、記憶を整理しています。記憶を整理する過程で、深い睡眠、いわゆるノンレム睡眠では、嫌な記憶を消去すると考えられています。
ノンレム睡眠は脳がリラックスした状態であるため、副交感神経が優位になっている呼吸法、つまり深い呼吸の可能性が高いと言えます。
代謝が落ちて疲労を感じやすくなる
呼吸が浅いと、代謝が落ちて疲労を感じやすくなる場合が多いです。
浅い呼吸により、二酸化炭素を吐き出し、酸素を取り込むという作業効率が低下し、全身の代謝が落ちてしまう傾向にあります。代謝が落ちると、エネルギーを産み出す力も落ちてしまうため、疲れやすくなります。
また、代謝が落ち、疲れやすくなると、運動を避けるようになり、筋力が低下する傾向にあります。そうすると、筋力の低下によって、代謝がさらに落ちるという悪循環を繰り返す可能性が高いです。
逆を言えば、深い呼吸をすることで、代謝率が上がり、疲労を回復することが見込まれると言えるでしょう。
筋肉にダメージが生じる
呼吸が浅いと、筋肉にダメージが生じることがあります。
ここでいう筋肉のダメージとはこわばり、肩こり、首こりのような症状のことを言います。
呼吸が浅くなると、筋肉の細胞内に酸素が行きわたりづらい状態になるため、、酸素を補おうと呼吸の数が増え、肩や首付近の筋肉にダメージが生じることが多くなることがあります。
また、呼吸の数を増やすために、首や肩、背中の筋肉を使ってしまうことで、筋肉に疲労がたまりやすい状態になってしまっている可能性が高いと言えるでしょう。
体が冷える
呼吸が浅いと、体が冷えることがあります。
浅い呼吸では、取り込める酸素が少なく、体内の酸素量が不足しがちです。少ない酸素は、脳や心臓など、生命の維持を司る器官へ優先的に送り込まれます。そうすると、末端の毛細血管は行きわたらないこともあります。
末端の毛細血管まで酸素が行きわたらないことで「冷え性」が引き起こされます。
冷え性が悪化すると、快適な睡眠を妨げられ、深く眠れなくなる可能性が高いです。そして、睡眠不足が続く場合、疲労回復がしにくくなると考えられています。
集中力が落ちる
呼吸が浅いと、集中力が落ちると言われています。
浅い呼吸では、体内に取り込まれる酸素量が少ないため、脳内の酸素が不足しがちです。脳内に酸素が行きわたらないと、集中力や思考力が落ちてしまうことが考えられます。
また、集中力や思考力が落ちることにより、仕事や勉強が効率的に進まなくなる場合があります。
加えて、自律神経の核となる脳内の酸素が不足すると、自律神経のバランスを崩すことにもつながってしまうことがあるため、注意が必要です。
浅い呼吸の治し方
浅い呼吸の治し方には、以下の5点が挙げられます。
- 鼻呼吸を意識する
- 深呼吸を習慣化する
- 腹式呼吸を意識する
- 適度な運動をする
- 姿勢を正す
鼻呼吸を意識する
鼻呼吸を意識すると、浅い呼吸が治ると言われています。
鼻呼吸とは、4~5秒かけてゆっくりと息を吐き、その後、ゆっくりと鼻から息を吸う方法です。
鼻からしっかりと肺の中の空気を吐き切ることで、深い呼吸になりやすくなるでしょう。
鼻からゆっくり空気を吐き出すことを意識することで、副交感神経が優位になる傾向があります。また、鼻呼吸をすると、脳や体に酸素が行きわたります。この場合、脳や体をリラックスさせることが見込まれるでしょう。
さらに、鼻呼吸は、鼻毛や鼻腔粘膜が外界の異物をブロックしてくれるというメリットがあります。加えて、鼻腔を通ることで、適切な温度や湿度の空気が入ってくるため、体内にスムーズに取り込みやすいというメリットもあります。
深呼吸を習慣化する
深呼吸を習慣化すると、浅い呼吸が治りやすいと言えます。深呼吸の手順は以下の通りです。
- リラックスした体勢になる
- 鼻からゆっくりと空気を吸い込む
- 口から少しずつ息を吐き出す
深呼吸を習慣化することで、浅い呼吸が深い呼吸に変化していくのを感じることを期待できます。また、呼吸のリズムが整い、深い呼吸をしやすくなる傾向にあります。
深呼吸をするには、意識的に呼吸するのが大切と言えます。つまり、呼吸に向き合う時間を確保すると、深呼吸が定着していく可能性が高いです。
深呼吸の習慣がつくと、無意識に深呼吸することが多くなるでしょう。
深呼吸習慣化デバイス「ston s」

- 「ston s」は、エナジードリンクでも、電子タバコでもない深呼吸を習慣化することを目的としたデバイス
- 罪悪感0で瞬間リフレッシュが可能
- 充電の必要がなく、どこでも持ち運びできる
腹式呼吸を意識する
腹式呼吸を意識すると、浅い呼吸が治る可能性があります。腹式呼吸の手順は以下の通りです。
- 背中を床につけて横たわり、ゆっくりと口から息を吐き出す
- 鼻からゆっくりと深く息を吸い込む
- もう一度口から息をゆっくりと吐き出す
- 1~3を繰り返す
腹の下部を引っ込める動作と膨らませる動作を繰り返すという腹圧の変化で、呼吸のリズムや深さが整う傾向にあります。
無理なく、毎日続けると、腹式呼吸は定着することが期待できます。まずは、1日5回行うことから始め、徐々に回数を増やしていくと良いと考えられています。
体の中の悪いものをしっかりと出し切るように、腹を凹ますことがポイントです。そして、吐く時間は、吸う時間の2倍かけるくらい、ゆっくりと息を吐き切ると良いと言われています。
適度な運動をする
適度な運動をすると、浅い呼吸が治るケースがあります。
適度な運動により、肺活量が向上するため、呼吸筋が鍛えられる傾向があります。そうすると、呼吸筋を用い、深い呼吸になりやすいと言えます。
例えば、ランニングやウォーキング、水泳などの有酸素運動をすると、肺活量の向上が見込めます。また、ヨガや気功、太極拳などの呼吸を意識する運動も、深い呼吸が定着する可能性が高いです。
さらに、呼吸を意識しながら運動をすると、筋肉がリラックスした状態になりやすいと言われています。そうすると、ストレッチ効果やトレーニング効果が望める場合が多いです。
姿勢を正す
姿勢を正すことで、浅い呼吸が治る場合が多いです。
姿勢が悪い場合、肺や腹を圧迫し、深い呼吸がしにくく、浅い呼吸になる傾向にあります。このとき、姿勢を正すと、深い呼吸をしやすいです。
また、パソコンやスマートフォンの使用時、前かがみや猫背になりやすいため、姿勢を正すことを意識すると良いでしょう。例えば、画面の高さや椅子の座り方、定期的な休憩を心がけると良いと考えられています。
浅い呼吸を改善するメリット
浅い呼吸を改善するメリットには以下の5点が挙げられます。
- 酸素を体に多く取り込める
- 悩みやストレスが軽減される
- 睡眠の質が改善する
- 免疫力が上がる
- 血圧が安定する
酸素を体に多く取り込める
浅い呼吸を改善するメリットの1つとして、酸素を体に多く取り込めることが挙げられます。
浅い呼吸を改善し、深い呼吸が定着すると、肺にしっかりと酸素が取り込めることが見込めます。そして、酸素を取り込む量が増えるため、血中酸素濃度も高くなり、体内に酸素が行きわたりやすいです。
また、体内の細胞に酸素が行きわたると、エネルギーの生産効率が上がるため、代謝がよくなり、疲労回復が期待できます。
さらに、酸素の供給量が増えることによって、細胞の再生や修復が促され、免疫力が向上することができるでしょう。
悩みやストレスが軽減される
浅い呼吸を改善すると、悩みやストレスが軽減されることが期待できます。
ストレスを感じている状態は、交感神経が活性化していると言えます。しかし、浅い呼吸を改善し、深い呼吸が定着すると、副交感神経が優位に働く場合が多いです。これにより、交感神経のバランスが調整され、悩みやストレスが軽減されると言えます。
具体的には、副交感神経が優位に働くと、ストレスの原因であるコルチゾールが減少すると言われています。また、深い呼吸が定着すると、ストレスや悩みを乗り切りやすくなるため、リラックス状態が増える可能性が高いです。
浅い呼吸が改善することで、自律神経のバランスが整え、心身の健康をサポートする重要な要素と言えるでしょう。
睡眠の質が改善する
浅い呼吸を改善することは、睡眠の質を改善する効果があると言われています。
浅い呼吸が改善し、深い呼吸が定着すると、リラックスできることや心拍数が安定することがあります。そうすると、眠りにつく際に、安眠が期待され、結果的に睡眠の質が改善すると言えるでしょう。
また、睡眠にも自律神経の働きが関係しているため、交感神経が活性化した状態では浅い眠りになりやすいです。しかし、深い呼吸により副交感神経が優位に働くと、体がリラックスし、安眠効果が期待できます。さらに、深い呼吸により心拍数が安定することでも、体がリラックスする場合が多いです。
免疫力が上がる
浅い呼吸を改善すると、免疫力が上がりやすいと考えられています。
浅い呼吸が改善し、深い呼吸が定着することで、酸素が体内の細胞に行きわたりやすくなります。体内の細胞のうち、免疫細胞にも酸素が効率的に供給されるため、免疫力が上がると言えるでしょう。また、深い呼吸により副交感神経が優位に働くと、体力が回復しやすくなることがあります。
具体的には、免疫細胞の中にある白血球やナチュラルキラー細胞が活性化され、病原体への抵抗力が上がる傾向にあります。
加えて、浅い呼吸が改善すると、体内の免疫システムが正常に働くため、結果、免疫力が上がる効果も期待できます。
血圧が安定する
浅い呼吸を改善することは、血圧の安定にもつながると言えます。
浅い呼吸が改善し、深い呼吸が定着することで、心拍数が徐々に下がり、血圧が安定する傾向にあります。また、血管の収縮が緩み、血流がスムーズになると血圧が安定する場合が多いです。
例えば、深い呼吸で、多くの酸素を取り込むと、血中酸素濃度が上がり、血管が広がると言われています。
また、自律神経が整ったり、ストレスが軽減されたりすることも血圧の安定に作用すると考えられています。
呼吸が浅い原因に関連するよくある質問
呼吸が浅い人の症状は?
呼吸が浅い人の症状として以下の5点が挙げられます。
- 疲れやすい
- 集中力が落ちる
- 体が冷える
- 免疫力が下がる
- ストレスを感じやすい
いずれの症状も、体内に酸素が行き渡ってないことが原因であると考えられます。
呼吸が浅いと、酸素をしっかりと取り込みづらいと言えます。その結果、血中酸素濃度が下がり、代謝も落ちる傾向にあるため、疲れがとれず、集中力が落ちることにつながる場合が多いです。加えて、脳内の酸素不足は、集中力の低下につながりやすいでしょう。
また、呼吸が浅いと、末端まで酸素が行き渡らないため、体が冷えやすくなります。
さらに、呼吸が浅い場合、自律神経のバランスが崩れやすいため、免疫システムやストレス細胞に影響を及ぼすことがあります。
呼吸が浅いか確認する方法はありますか?
ゆっくりと息を吐いてみるという方法があります。もし、20秒未満で止まってしまう場合は呼吸が浅いと言えます。
呼吸の浅い人は、胸郭や横隔膜の動きが制限されている場合が多いです。その場合、吸い込む空気の量が限られるため、吐き出す空気も減り、長い時間をかけて吐き切ることが難しいと言えます。 また、呼吸に関わる筋肉、いわゆる呼吸筋を鍛えないと、肺活量が増えないため、浅い呼吸を繰り返す傾向があります。そのため、浅い呼吸を繰り返してしまう人は、深い呼吸を意識して行うことが重要です。深い呼吸をすることによって、酸素を取り込む量が増えたり、呼吸筋が鍛えられたりして、長い時間をかけて息を吐くことできるでしょう。
【監修者プロフィール】

江東こころのクリニック院長
谷本 幸多朗医師
九州大学医学部卒業後、帯広第一病院にて救急医療や外科及び内科の研修を経験する。
2013年より久喜すずのき病院にて精神科急性期医療を後期研修し精神保健指定医となる。
2018年より江東区にて一般メンタルクリニックに加えて認知症デイケアを併設した物忘れ外来も行う精神科クリニックである江東こころのクリニックを開業し、現在に至る。
▼主な経験
- 精神保健指定医の経験あり
- 製薬会社主催の各講演会や地域の医療職対象の勉強会において講演や座長の経験多数あり