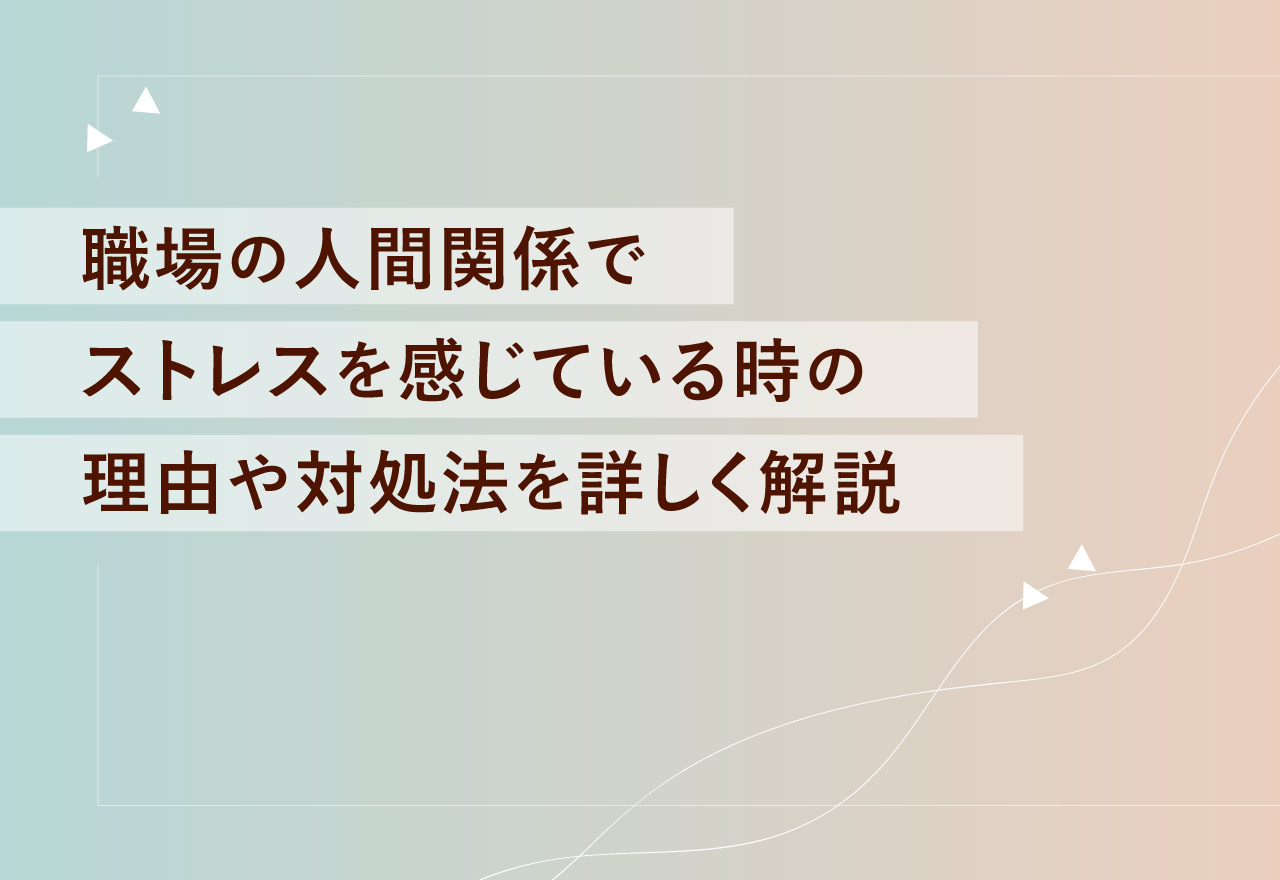目次
職場の人間関係がストレスになる理由
職場の人間関係がストレスになる主な理由として、以下のものが挙げられます。
- 職場のコミュニケーションが少ない
- 自分の意見を言えない
- 業務内容や労働環境が厳しい
- 職場で孤立している
- 職場の競争が激しい
- 気が合わない人がいる
- ハラスメントをする人がいる
職場のコミュニケーションが少ない
職場でのコミュニケーション不足が原因で、職場の人間関係がストレスに感じることがあります。周囲とのコミュニケーションが不足すると、自分の意見や考えが正確に伝わらない恐れがあるからです。
また、自分と相手で認識の相違や齟齬が生じると、苛立ちや不満を感じることも少なくありません。さらに、コミュニケーションが不足した状態では、業務上の混乱や問題も発生しやすいです。
こうした状況では良好な人間関係を築くのが難しくなり、職場の人間関係がストレスの原因になりがちです。
自分の意見を言えない
自分の意見を言えないことは、職場の人間関係がストレスになる理由になり得ます。
自分と相性が悪い人や、怖いと感じる人には、意見を言いづらいことが多くあります。相手に対して気になる点や不快に思ったことなどを指摘できないと、ストレスが溜まりやすいです。
さらに、上司や上長からのパワハラで萎縮してしまい、自分の意見が言いづらくなる状況もあります。そのような環境に身を置き続けると、心身に不調をきたす恐れがあるため、部署異動や転職を検討することも1つの手段であるとされています。
業務内容や労働環境が厳しい
業務内容や労働環境が厳しい職場では、人間関係に対してストレスを感じる可能性が高いです。業務量の多い会社や人手の足りない職場では、休暇が取りづらいため疲労が蓄積しやすく、ストレスを感じることも多くあります。
営業職のような目標が設定されている職場でも、クライアント対応などにより時間外勤務が生じることが想定され、ストレスを感じやすい傾向があります。
上記のように、ストレスを抱える人が多い環境では、良好な人間関係が築きにくく、人間関係自体がストレスの要因となりがちです。
職場で孤立している
職場で孤立していると、仕事にさまざまな悪影響が生じやすく、人間関係にストレスを感じる要因にもなり得ます。
部署や担当者によって役割は異なるため、仕事を進める上で他の社員との連携が必要になることも少なくありません。
しかし、職場で良好な人間関係が築けていないと、仕事に関する連絡や相談が円滑に進まない可能性が高まります。
また、職場で孤立していると他の社員と業務を分担するのが難しくなり、一人で対応しようとして負担を抱えやすいです。
職場の競争が激しい
職場の競争が激しいと、良好な人間関係を築きにくくなり、結果としてストレスを感じやすくなる場合があります。
営業職などの職場に見られる特徴として、社員間で成績を競い合う傾向が挙げられます。競争心が盛んな組織風土では、緊張感のある人間関係や雰囲気が生まれやすいです。また、競争が過熱すると、社員間での対立や敵対的な態度が形成される可能性もあります。
気が合わない人がいる
職場の人間関係がストレスになる理由として、気が合わない人が職場にいることも挙げられます。職場で仕事を進めるには、気が合わない人とも意思疎通が必要なシーンがあり、心理的な負担が大きくなりやすいです。
また、同じチームやプロジェクトに属していると、細かなやり取りが必要になるため、一定の距離を保つのが難しく、人間関係にストレスを感じやすいです。
ハラスメントをする人がいる
職場にハラスメントをする人がいると、人間関係に対してストレスを感じやすい傾向にあります。自身がハラスメントの対象になっている場合、相手とのコミュニケーションに苦痛を感じる場面が多くなりがちです。
自分ではなく他者がハラスメントを受けている状況も、職場での人間関係に悪い印象を抱きやすいとされています。自分がハラスメントの対象になる可能性があるという懸念から、人間関係に気を遣ってストレスを感じやすくなる可能性があるからです。
職場でハラスメントが横行している場合の対応として、人事担当者や社内外のハラスメント相談窓口に相談し、部署異動や配置転換を求める方法が挙げられます。問題が解決しない場合は、転職を選択することも有効な手段として考えられます。
職場の人間関係に関するストレスの対処法・対策
職場の人間関係に関するストレスの主な対処法や対策は、以下の通りです。
- 職場の人間関係に対する考え方を改める
- 深呼吸をする
- 自分と周囲を比べ過ぎない
- 気分転換をする
- 周囲の人に相談する
- 仕事仲間に話を聞いてもらう
- 人事相談をする
- 部署異動をする
- 転職や休職をする
職場の人間関係に対する考え方を改める
職場の人間関係に対する考え方を改めることは、ストレスへの対策として有効な手段と言われています。
相手の考えや行動に理解や同調を求めず、仕事上の関係だと納得して受け入れることは、ストレス軽減に有効な方法の一つです。
職場での基本的な目的は業務を遂行することであり、プライベートのように親密な人間関係を築くことは必須ではないと考えられています。
無理に価値基準を合わせようとせず適度な距離感を保つことで、人間関係に関するトラブルや悩みが起きにくくなる可能性が高いです。
しかし、距離感を保つことに意識を向けすぎて、必要最低限のコミュニケーションが疎かになると、業務が円滑に進みにくくなる可能性があります。あくまでも相手の考えや立場を考慮し、適切な関係を維持することが重要と言えるでしょう。
深呼吸をする
深呼吸により心と身体がリラックスできる時間を作り出すことが、職場の人間関係のストレスへの対策に繋がる場合があります。深呼吸によって多くの酸素が取り込まれると、身体全体に酸素が行き渡りやすくなると考えられているためです。
身体に酸素が行き渡ると、脈拍が安定するほか、ストレスホルモンの分泌が抑制され、心身のリフレッシュが期待できます。深呼吸を行う際は、以下の手順で行うことも、おすすめの方法の1つであると言われています。
- 静かな状況でリラックスできる姿勢になる
- 鼻から空気を取り込み、腹部を膨らませる
- 時間をかけて口から息を吐き出す
深呼吸習慣化デバイス「ston s」

- 「ston s」は、エナジードリンクでも、電子タバコでもない深呼吸を習慣化することを目的としたデバイス
- 罪悪感0で瞬間リフレッシュが可能
- 充電の必要がなく、どこでも持ち運びできる
自分と周囲を比べ過ぎない
職場の人間関係に関するストレスの対策の1つとして、自分と周囲を比べ過ぎないことが挙げられます。
周囲と自分を比較して、劣っている部分に目を向けてしまう人は、ストレスを感じやすい場合が多いです。結果が数値で示される職種では、優劣が分かりやすく比較しやすいため、落ち込みやすい傾向にあります。
自信がないと組織に対して後ろめたさを感じ、職場における自身の役割に、意味を感じにくくなる可能性があります。
結果的に、周囲に負担をかけていると思ったり、居心地の悪さを感じたりしやすくなり、ストレスが増えてしまうことが多いです。
気分転換をする
職場の人間関係にストレスを感じた際の対処法として、気分転換で気持ちを切り替えることが挙げられます。ストレスを感じると感情的になりやすく、冷静さを失うことも少なくありません。
気分転換に繋がるような行動を取ることによって、考えを整理し、気持ちを落ち着けやすいため、ストレス軽減の効果が期待できます。
また、気分転換を兼ねた行動で、ストレスの原因から離れることができる場合もあります。代表的な気分転換の手段は、以下の通りです。
- 外出や遠出をする
- 趣味の時間を楽しむ
- ショッピングを楽しむ
- 関係性の良い同僚や友人と交流する
周囲の人に相談する
周囲の人に相談することで、職場の人間関係のストレスを解消できる場合もあります。ストレスや悩みを抱えたままだと、感情が高ぶり、的確な判断が難しくなることが多いです。
そのような時は、家族や信頼のおける友人など、親しい人に話を聞いてもらうことが有効と考えられます。
家族や友人であれば、職場のしがらみや利害に左右されることが少なく、客観的な意見を聞きやすいです。
さらに、自分の気持ちを誰かに話すことで、考えを整理したり、精神的な負担を軽減したりする効果も期待できます。
仕事仲間に話を聞いてもらう
仕事仲間に相談することが、職場での人間関係によるストレスの解消に役立つ場合もあります。仕事仲間は、職場の人間関係や社内の状況を把握していることが多いです。そのため、ストレスの背景についても理解を得やすく、第三者の視点から適切な見解が期待できます。
さらに、仕事仲間も同じようなストレスや悩みを抱えている場合があります。仕事仲間の経験や解決策を参考にすることで、自身のストレスを解消できることも少なくありません。なお、デスク周辺や休憩室など、相談内容が他人に聞こえやすい場所は避けた方が良いとされています。
人事相談をする
人事相談を活用すれば、職場の人間関係の問題が解消され、ストレスに対処できる可能性があります。人事部といった社内の相談窓口では、一般的に社員に対して守秘義務を負った上で相談を受け付けているため、職場の問題について相談しやすい傾向にあるためです。
人事相談によって、所属する部署やチームの変更などが実現することもあります。新しい環境に移ることで、気持ちを一新して人間関係を構築できることが多く、効果的な対処となる可能性が高いです。
なお、人事相談の際は、問題の詳細や具体的な被害について、できる限り詳しく伝えることが望ましいとされています。
部署異動をする
部署異動をすると、人間関係のストレスが解消される見込みが大きいです。その理由は、相性の良い環境と出会うことで、職場での人間関係を新たに築ける可能性があるからです。
さらに、相性が良くない人やハラスメントをする人との接触が減ることで、ストレスの軽減が期待できます。
しかし、部署異動が承諾されても、望んだ部署や配置にならない場合もあります。さらに、異動先の人間関係に馴染めないと、新たなストレスの原因になる可能性が高いです。実際に部署移動をする際には、こういったリスクも含めて相談をすることが大切だと言えるでしょう。
転職や休職をする
職場の人間関係におけるストレスへの向き合い方として、転職や休職を検討することも有効であると言われています。
転職によって働く環境を変えると、職場での人間関係をリセットでき、ストレスを解消できる可能性が高まります。
転職の準備を進めることで、現在の職場以外にも選択肢があるという安心感が得られやすいです。その結果、精神的な余裕が生まれ、ストレスが軽減することもあります。
一方で、休職して一時的に職場から距離を置くというのも選択肢の一つです。職場を離れている間は人間関係を気にすることが減り、ストレス軽減が期待できます。
しかし、転職をしても新しい職場の人間関係でストレスを感じる可能性があります。また、休職をすると、所得の低下やキャリアへの影響といった問題が生じることが多いです。
転職や休職をする際には、第三者に相談をするなど、冷静な判断に基づいて進めることが重要なポイントの一つであると考えられます。
職場での人間関係でストレスを感じることの悪影響
職場での人間関係でストレスを感じることの悪影響には、主に以下のようなものがあります。
- 精神的なダメージを受けやすくなる
- 注意力が低下する
- やる気が起きにくくなる
- プライベートを楽しめなくなる
- 睡眠不足になる
- 身体の不調に繋がる
- 疲労が溜まる
心理的な影響
精神的なダメージを受けやすくなる
職場での人間関係によるストレスは、精神的なダメージを受けやすくなることが多いです。
また、ストレスが溜まると思考がマイナスに傾き、精神的にも脆くなりがちです。心が繊細になっている状態では、小さなトラブルでも傷つきやすい傾向にあり、精神的なダメージを受けやすくなります。
注意力が低下する
職場の人間関係でストレスを感じていると、注意力が散漫になることが少なくありません。ストレスが溜まりパフォーマンスが低下すると、注意力が落ちてミスが増える傾向があります。そのため、今まで問題なくこなせていた仕事でも小さな間違いをしてしまったり、予定の失念が起こりやすくなります。
さらに、注意力の低下によりスケジュールの管理や情報伝達などが不十分になることが多いです。その結果、予定に間に合わなかったり、仕事仲間との連携が取りにくくなったりする可能性があります。
やる気が起きにくくなる
職場の人間関係でストレスを感じることの悪影響の一つが、やる気が起きにくくなることです。職場の人間とはコミュニケーションを取る機会が多いですが、苦手な人や嫌いな相手だとストレスが溜まりやすいです。
ストレスを抱えた状態では仕事に集中しづらく、モチベーションも低くなる傾向にあります。モチベーションが維持できないとやる気が低下し、仕事の効率や生産性に影響が出やすいです。
やる気が出ず、仕事のクオリティが低下すると、社内での評価が下がる可能性もあります。社内での評価が下がれば、給与や待遇にも悪影響を及ぼしかねません。
プライベートを楽しめなくなる
職場での人間関係によるストレスが原因で、プライベートを楽しめない状況に陥ることもあります。ストレスが蓄積すると精神衛生が悪化し、気持ちの落ち込みが続くような状態になる可能性が高いです。
例えば、趣味を楽しめなくなることや、日常生活を送るのみで気分が落ち込んでしまうことが挙げられます。
これらの現象は、ストレスにより脳の前頭前野と呼ばれる部分の働きが抑制されるためとされています。
前頭前野は思考や衝動を司ると言われており、モチベーションや喜怒哀楽といった感情に影響を及ぼすことが多いです。
身体的な影響
睡眠不足になる
職場での人間関係によるストレスは、睡眠不足を引き起こすことがあります。ストレスから来る不安感やプレッシャーの影響で精神的に落ち着けず、入眠しにくくなる場合があるためです。
入眠しづらくなると就寝時間が乱れてしまい、結果として睡眠不足になることがあります。さらにストレスを抱えていると、自律神経のバランスが崩れやすくなるとも言われています。
自律神経が不安定なまま就寝すると、中途覚醒が生じたり、深い眠りに入りにくくなったりすることが少なくありません。
睡眠不足が続くと心身のコンディションが悪くなり、ストレスに対する抵抗力が低下する可能性があります。
身体の不調に繋がる
職場の人間関係が原因でストレスを抱え過ぎると、身体の不調に繋がる場合が多いです。心理的なストレスにより身体が緊張すると、自律神経の一種である交感神経が活発な状態が継続しやすくなると言われています。この状態では、頭部や首回り、肩などの筋肉がこわばって血管が収縮する傾向にあります。そのため、血流が悪化し、肩こりや頭痛などの不調を引き起こす可能性が高いです。
疲労が溜まる
職場の人間関係で感じるストレスは、疲労が溜まる原因にもなります。ストレスが溜まると、身体が緊張している状態が続きやすく、心や身体の安らぎを感じられる時間が削られてしまうことが多いです。
ストレスの蓄積は睡眠不足を引き起こす原因にもなり、睡眠による疲労回復効果が発揮されにくい状態に繋がりやすいです。
さらにストレスは自律神経のバランスが崩れる要因の1つともされています。自律神経のバランスが崩れると、身体が疲れていると感じやすい傾向にあります。
職場の人間関係で気をつけるべきこと
職場の人間関係で主に気をつけるべきことは、以下の通りです。
- 感情的な対応をしない
- チームワークを重んじる
- 挨拶をする
- 人の話をきちんと聞く
- 時間を守る
- 笑顔でいる
- 報連相をきちんとする
- 整理整頓をする
感情的な対応をしない
職場の人間関係で気をつけるべきこととして、感情的にならないことが挙げられます。感情的な態度や振る舞いをすると、周囲から未熟で節度がない、厄介な人と思われがちです。
結果として、人間関係のトラブルにつながる可能性があるため、感情的にならないことが重要とされています。
また、落ち着いてコミュニケーションを取ることで、生産的なやり取りがしやすくなります。以下は、感情的になることを防ぐための具体例です。
- 相手の考えを受け入れ、理解を試みる
- すぐに言い返すのではなく、考えをまとめてから返事をする
- 前向きな言葉で伝えることを心掛ける
- 深呼吸をしてリラックスする
- 休息や睡眠を取って気持ちを安定させる
- 勝ち負けにこだわらず、トラブルを避けることを意識する
- 問題の相手や場所から距離を置く
- 感情を言葉にして、俯瞰して見つめる
チームワークを重んじる
職場の人間関係では、チームワークを重んじる姿勢を持つことが大切だと言えるでしょう。チームワークを軽視する態度や言動は、周囲からの信頼喪失や、職場の雰囲気を悪化させる原因になりやすいです。
職場の人間からの評判や印象が悪くなると、職場の環境に溶け込めず孤立してしまい、ストレスが溜まることもあります。
職場で良好な人間関係を築けないと、チーム内のモチベーションを維持することが難しく、業務効率や生産性が下がりかねません。こうした理由から、チームワークを重んじて周囲と良好な関係を築くことが大切と言えます。
チームワークを重んじるための代表的な行動として、丁寧な話し方やマナーを意識した立ち振る舞いが挙げられます。また、共通の趣味や話題について話したり、仕事に関する提案や今後の目標を共有することも、良好な人間関係を築く方法の一つです。
挨拶をする
職場の人間関係において、挨拶は重要な要素とされています。挨拶をしない人は、礼儀に欠け、常識やマナーがないという印象を持たれやすいからです。
相手からのイメージが悪くなると、良好な人間関係を築くのが難しくなりがちです。逆に、適切なタイミングで挨拶をすると、礼儀正しい人だというポジティブな印象を持たれやすいと言えるでしょう。
また、挨拶が習慣化すると、職場の人との会話の敷居が低くなる可能性が高いです。これによりコミュニケーションが円滑になると、意思疎通がスムーズになり、業務効率の向上やストレスの軽減が期待できます。挨拶をするタイミングと伝え方の例は、以下の通りです。
| タイミング | 伝え方 |
| 出勤した時 | おはようございます、こんにちはなど |
| 退勤する時 | お先に失礼します、お先に帰らせていただきます、お先にお暇させていただきますなど |
| 他の人が先に退勤した時 | お疲れ様でした、ご苦労様でした |
| 職場の人と会った時 | おはようございます、お疲れさまですなど |
| 自分が外出する時 | いってきます、いってまいりますなど |
| 自分が帰って来た時 | ただいま戻りました、戻ってまいりましたなど |
| 他の人が帰って来た時 | お疲れさまです、おかえりなさいなど |
| 取引先の人に会った時 | 先日はたいへんお世話になりました、お世話になっておりますなど |
挨拶をする際は、相手に伝わる声の大きさや、明るい雰囲気を意識することが大切と言われています。また、敬語を用いて挨拶すると、相手を敬う意思を伝えやすい傾向にあります。
人の話をきちんと聞く
人の話をきちんと聞くことも、職場の人間関係で気をつけるべきポイントの一つです。話をしっかり聞く姿勢を相手に感じてもらえると、良好な人間関係を築きやすくなります。
意見が合わない場合でも、批判や否定をせずに理解しようとする姿勢を見せることが効果的とされています。
この人は話を聞いてくれるという信頼を得られると、相手もこちらの話を聞いてくれる見込みが大きいです。
両者がともに話しやすい関係になれば、円滑なコミュニケーションや相互理解の深まりが期待できます。
しかし、相手が話すのを聞いているのみでは、受け身な姿勢に見えてしまいがちです。話の途中で適度に相槌を挟んだり、気になった部分について尋ねてみたりすることで、意欲的に話を聞く姿勢が伝わりやすくなります。
時間を守る
時間を守る意識は、職場での人間関係において大切なポイントとされています。期限内に仕事を完遂したり、指定の時間までに成果物を提出したりするなど、時間を守って行動することは重視されやすいです。
指定された時間を守って行動すると周りの人からの印象が良くなり、信頼を獲得しやすい傾向にあるためです。
また、時間を守ることは、協力して業務に取り組みやすいという評価にも繋がり、職場の人間関係を良好に保ちやすくなります。時間を守る人として評価されるには、時間に余裕を持って行動することが効果的とされています。
具体例として挙げられるのが、会議や商談が開始されるギリギリの時刻ではなく、5〜10分前には現地に居て用意が済んでいることなどです。また、資料や報告書も期日当日ではなく、前もって提出することが望ましいと言えるでしょう。
笑顔でいる
職場の人間関係においてポイントと言われていることの一つに、笑顔を意識することが挙げられます。
笑顔でいると柔和な雰囲気が生まれやすく、相手に安心感を与えて話をしやすくなる効果が期待できるためです。
明るい印象を持たれることで声をかけやすくなり、円滑なコミュニケーションが図りやすくなります。
これらは、職場の雰囲気を良くすることにも繋がるため、笑顔でいることは大切と言えるでしょう。なお、タイミングやシチュエーションに応じて笑顔を見せることが望ましいとされています。
報連相をきちんとする
職場の人間関係で気をつけたいポイントの一つは、報連相をきちんとすることです。報連相(報告・連絡・相談)を必要に応じて行うことは、職場の信頼関係を築く上で重要だとされています。
報連相を重視する姿勢から責任感や協調性が感じられ、良い印象を持たれやすいためです。報連相によって情報や進捗を共有することで、認識の違いやコミュニケーション不足から生じるトラブルを防ぐことも期待できます。
また、トラブルが発生しても、適切な報連相ができていればミスや失敗の影響を抑えられる場合があります。報連相で意識するべきポイントとして挙げられるのは、以下の通りです。
- 期日や時間に間に合わない可能性がある場合は、できる限り早く連絡する
- 要点を事前に整理し、結論を先に述べる
- 個人の意見に頼らず、事実ベースで話をする
- 何かを尋ねる際は、可能な限り自分自身の見解や代案を用意する
- 内容や緊急性の高さに合わせて、口伝えやメールなどの手段を柔軟に使い分ける
整理整頓をする
整理整頓も、職場の人間関係において気をつけるべきこととして挙げられます。デスクやロッカーが整理整頓されていると業務を効率的に進めやすくなり、周囲からの評価向上にも繋がります。
評価が向上するとコミュニケーションも取りやすくなり、職場の人間関係を良好に保てる見込みも大きいです。
例えば、仕事上必要な書類をすぐに共有できたり、仕事仲間から借りたものをなくさずに返したりなどの行動が、職場の人間関係を築く基礎になると考えられます。
職場の人間関係のストレスに関するよくある質問
人間関係の悪い職場の特徴は?
人間関係の悪い職場の特徴として、嫌がらせやハラスメントが多いこと、労働環境や労働条件が悪いことなどが挙げられます。
また、独裁的な企業文化やあることや待遇に不満を持つ人が多いことも、人間関係の悪い職場の特徴として見られやすいです。
嫌がらせやハラスメントをする人がいると、職場の雰囲気が悪化し、人間関係も悪くなりやすい傾向にあります。
さらに、低賃金や長時間労働によるストレスで精神的な余裕を失うと、良好な人間関係が築きにくくなると考えられます。
職場の3大ストレス要因とは何ですか?
職場の3大ストレス要因として挙げられるのが、業務でのミスや責任の発生、過剰な業務量、人間関係などです。(※)
例えば、後輩が繰り返しミスを起こしたり、人手不足によってキャパシティを超える業務量を任されたりすることがストレスになり得ると考えられます。
また、人間関係の面では、仕事仲間が相手によって態度を変えていると感じた時や、仕事に必要な知識や常識が相手に欠けていると感じた際などに、ストレスが生じることも想定できます。
※「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」に記載(2024年11月調査時点)
職場の人間関係でストレスを感じやすい人の特徴は何ですか?
理想が高いことや意見の主張が苦手なこと、周りの評価に敏感であることなどは、職場の人間関係でストレスを感じやすい人に多く見られる特徴です。
また、自尊心や劣等感が強い、真面目すぎるなどの性格も、ストレスを感じやすい要因とされています。
上記のような性格の人は、コミュニケーションを取る際に疲れを感じやすい傾向にあります。さらに、言動によっては人間関係のトラブルに発展するケースも見受けられ、それがストレスの原因になることも少なくありません。
職場の人間関係のストレスをチェックする方法はありますか?
職場の人間関係のストレスをチェックしたい場合は、ストレスによる症状が出ているかを確認することが有効であると考えられます。例えば、以下のような症状に該当する場合、ストレスを過度に受けている可能性があります。
- 気分が落ち込む
- モチベーションが下がる
- 注意力が散漫になる
- 趣味を楽しめない
- 些細なことで気が滅入る
- 将来に希望が持てない
- 感情が高ぶりやすい
- 涙もろくなる
- すぐに疲れてしまう
- 思考がまとまらない
- 自己価値を感じられない
- 外見に無頓着になる
- 人と会いたくなくなる
- 食欲が低減する
- 暴飲暴食をしてしまう
- 飲酒が増える
- 呼吸が乱れやすい
- 眠りが浅くなる
- 長時間寝てしまう
- 身体が重く感じる
- 頭痛や肩こりがする
- 耳鳴りがする
- 蕁麻疹が出る
- 便秘や下痢になる
【監修者プロフィール】

江東こころのクリニック院長
谷本 幸多朗医師
九州大学医学部卒業後、帯広第一病院にて救急医療や外科及び内科の研修を経験する。
2013年より久喜すずのき病院にて精神科急性期医療を後期研修し精神保健指定医となる。
2018年より江東区にて一般メンタルクリニックに加えて認知症デイケアを併設した物忘れ外来も行う精神科クリニックである江東こころのクリニックを開業し、現在に至る。
▼主な経験
・精神保健指定医の経験あり
・製薬会社主催の各講演会や地域の医療職対象の勉強会において講演や座長の経験多数あり